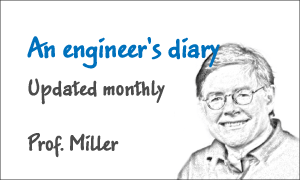JMAGは、スクリプトによってほぼすべての機能を操作できます。これまでユーザーサイトで限定公開していたスクリプトサンプルを、どなたでも利用できる場所に公開しました。
サンプルは主にPythonで記述されており、一般的なプログラミング知識で簡単に扱えます。さらに、スクリプトの記述方法や活用例を解説したマニュアルも併せて公開しましたので、初めての方でも安心してご利用いただけます。解析や設計の自動化、効率化を進めたい方は、ぜひこのライブラリをご活用ください。今後さらにサンプルを充実させていきますので、スクリプトを使った柔軟なワークフロー構築にお役立てください。
JMAGスクリプトライブラリ
-
[S0011] 部品表面を熱伝達境界条件の対象に設定する
熱解析スタディにて、セットで定義された面を対象に熱伝達境界条件を設定します。
-
[S0010] 自動メッシュ生成手法を手法3の要素サイズ自動決定でセットアップする
2次元磁界解析のメッシュプロパティをスライドメッシュの手法3(要素サイズ自動決定機能 新手法)に設定します。
-
[S0009] メッシュグループを対象とした部品・面・エッジの計算設定を追加する
対象をメッシュグループとする部品計算、面計算、エッジ計算を作成します。
-
[S0008] 解析条件のタイプを指定して設定されている条件を取得する
解析条件のタイプ名を指定して、スタディに設定されている条件を取得します。タイトルやインデックスを使用しない取得方法です。
-
[S0007] プロジェクトファイルと同フォルダに画像サイズを指定してイメージをエクスポートする
JMAG-Designerのモデル表示の画像イメージをファイルとして、開いているプロジェクトファイルと同じフォルダにエクスポートします。
-
[S0006] 指定した名前の部品の面積または体積を取得する
解析対象のモデルの部品、または部品グループの名前を指定して、3次元では体積、2次元では面積を取得します。
-
[S0005] 着磁材料部品の配向方向着磁パターンをパラレル円周パターン(任意磁化方向)に設定する
磁界解析において、着磁材料の設定された部品のプロパティにて配向方向の着磁パターンをパラレル円周パターン(任意磁化方向)に設定します。
-
[S0004] 磁界過渡応答解析のスタディプロパティのステップコントロールに定常判定条件を追加する
磁界過渡応答解析においてステップコントロールに、定常状態に到達したら解析を終了させるための定常判定条件を設定します。
-
[S0003] 回路にPWM120度通電3相素子を配置する
磁界過渡応答解析スタディ、または統合解析スタディの回路にPWM120度通電(3相)マクロ素子を配置します。
-
[S0002] 原点から指定半径内の部品すべてを回転運動条件の対象に設定する
磁界解析スタディの解析モデルにおいて、原点から指定半径以内にある部品を対象に回転運動条件を設定します。
-
[S0001] 2D磁界解析でX軸上のエッジすべてを回転周期境界条件の対象に設定する
2次元の磁界解析スタディの解析モデルにおいて、X軸上のX>=0にあるエッジに対して周期境界条件を設定します。
-
[S9389] PAMインバータのスイッチングタイミングを設定するスクリプト
PAMインバータのスイッチングタイミングを設定するスクリプトを例示します。
-
[S9326] 複数ケースで指定したケースのラベルと応答値を取得するスクリプト
複数ケースで指定したケースのラベルと応答値を取得するスクリプトを例示します。
-
[S9173] 直流重畳電流点列を作成し電流条件に設定するスクリプト
スクリプトで直流重畳電流点列を作成し電流条件に設定したい。
-
[S8635] 形状エディタで直方体を作成するスクリプト
形状エディタで直方体を作成するスクリプトを例示します。
-
[S8625] 材料と周波数から表皮厚さを設定するスクリプト
材料と周波数から表皮厚さを設定するスクリプトを例示します。
-
[S8569] 形状エディタで、重複節点を削除するスクリプト
形状エディタで、重複節点を削除するスクリプトを例示します。
-
[S8620] セクショングラフの結果をExcelファイルの任意位置(シート、セル)に貼り付けるスクリプト
セクショングラフの結果をExcelファイルの任意位置(シート、セル)に貼り付けるスクリプトを例示します。
-
[S8562] 範囲選択して部品のグループ化を行うスクリプト
範囲選択して部品のグループ化を行うスクリプトを例示します。
-
[S8561] 周波数応答解析(FQ)の電流値を位相ごとの値として出力するスクリプト
周波数応答解析の電流値を位相ごとの値としてスクリプトで出力したい。また、[ポスト計算スクリプト]で使用したい。