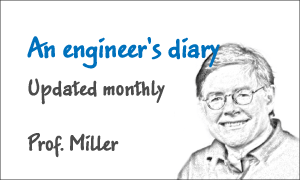「想像力は知識よりも重要である。」
考え抜く力と確かな実践力をもつ、社会に貢献する人材を育てる

企業での後輩育成の経験から、想像力を働かせて考えぬき手を動かす大事さと、社会でのコミュニケーションの重要性を学生に熱心に伝えています。
研究活動を通してそれらを議論し、実践することを大切にされている大口先生にお話しを伺いました。
2002年3月 東京都立大学大学院 工学研究科 博士課程修了 博士(工学)
2002年4月~2018年3月 富士電機株式会社
2018年4月~現在 東海大学 工学部 電気電子工学科
企業に在籍していた頃、後輩の育成に携わりました。その中で、大学、特に研究室に配属された後にどのような教育を受けると企業で活躍できるのかを考えるようになりました。
研究テーマ:
(1) たとえ僅かであっても、改善の余地の可能性があるなら探求してみる
(2) シミュレーションと実機の溝を埋める
(3) なぜそうなるのかを考え抜く
研究理念:
回転機技術の革新を通じ、カーボンニュートラル社会の実現と環境負荷の低減に寄与する
研究概要:
回転機とパワーエレクトロニクスを軸として研究活動を行っています。シミュレーションが多いのですが、最近少しずつ実験もできるようになってきました。
2025年4月現在、修士2年生2名、修士1年生4名、卒研生14名が在籍しています。卒研生のうち4名が留学生です。私が所属する電気電子工学科では3年次の秋学期から研究室に配属となります。そのため、秋学期からは在籍学生が10名ほど増えることになります。3年次生向けのゼミは「永久磁石同期モータ設計入門」をテキストとして輪講形式で行っています。また、ゼミの中でJMAG-Express Onlineを活用しています。最後の仕上げとして、私からモータの仕様を提示し、その仕様を満たす永久磁石同期モータの設計を課題としています。効率を体積で割った値を評価指標とし、各学生の設計結果をレビューします。同じ仕様でも、設計結果がまったく異なるところに面白みを感じますし、学生にもそう感じてもらえたら良いなと思いながらレビューします。
4年次になると卒業研究がスタートします。卒業研究は複数名または1人1テーマとしています。研究成果が得られた場合には3月の電気学会全国大会で発表するようにしています。
修士になると、1人1テーマで研究を遂行します。電気電子工学科の各教員の研究室の学生が1つの部屋で研究活動に取り組むようになります。修士の学生の居室では研究室ごとにスペースが与えられます。
実験室は2名の教員が1部屋を共有して使用しており、学生が解析や実験を行う場所となっています。
 修士の学生の写真
修士の学生の写真
 実験室の写真
実験室の写真
【1】回転機の高効率化
本研究では特に漂遊負荷損に着目した研究を行っております。漂遊負荷損は大形機では設計段階で考慮されていますが、中・小形機でも仕様によってはその影響が無視できないのではないかと考え研究しております。漂遊負荷損として、鉄心の面内渦電流損やかしめ部で発生する渦電流損、素線の循環電流損と渦電流損を対象として研究に取り組んでいます。
本研究はテーマ(1)に関連します。また、富士電機株式会社との共同研究です。
 図1:固定子鉄心の面内渦電流損解析、電流密度ベクトル
図1:固定子鉄心の面内渦電流損解析、電流密度ベクトル
 図2:かしめ部で発生する渦電流損解析、電流密度コンター図(上に赤い枠で囲った部分の拡大図を示しています)
図2:かしめ部で発生する渦電流損解析、電流密度コンター図(上に赤い枠で囲った部分の拡大図を示しています)
 図3:素線の循環電流損と渦電流損の解析、電流密度コンター図
図3:素線の循環電流損と渦電流損の解析、電流密度コンター図
【2】ロボット用モータの高性能化
人と共存するロボットは、人との接触等が生じても安全であることが求められており、バックドライバビリティの向上が求められています。バックドライバビリティ向上の1アイテムとしてコギングトルクの低減が挙げられます。以前、JMAGを用いてコギングトルクの最小化と無負荷誘起電圧の最大化の最適化問題に取り組みました。現在は、解析と実験の両面から低コギングトルク化に取り組んでいます。解析モデル、実機、コギングトルク評価装置の写真を示します。現状では、コギングトルクの解析に対し実測値が大幅に高く、実機のコギングトルクが大きくなる原因の究明が今後の課題として挙げられます。
本研究はテーマ(2)に関連します。また、トヨタ自動車株式会社との共同研究です。
 図4:ロボット用モータの解析モデル
図4:ロボット用モータの解析モデル


ロボット用モータの実機の写真
 コギングトルク評価装置の写真
コギングトルク評価装置の写真
【3】可変界磁同期機
電動車両用モータは低速大トルクかつ高速回転が求められています。低速大トルクを高効率に得るには界磁は高い方が適していますが、最高回転速度を高くすることができません。一方、界磁を低くして最高回転速度を高めると、低速大トルクを得るのに大電流が必要となり、低速での高効率化が困難となります。そこで、界磁を可変できる一方式である永久磁石と電磁石を界磁とするハイブリッド界磁形同期機の研究に取り組んでいます。株式会社明電舎が提案した構造を参考にロータをIPMとし、突極比の増加を目的として磁石を2層配置としました。ベースのモデルは電気学会ベンチマークモデルのDモデルです。JMAGで損失解析を行って提案機とDモデルの効率マップを描画し、比較しました。結果、提案機は低速域では界磁損があるため高効率化が困難ですが、高速域では界磁電流を流さずに運転することで優位性があることがわかりました。よって、提案構造は高速走行が多い車両に適していると考えています。さらに、機械強度は未検討ですが、最高回転速度の増加が可能であることを明らかにしました。そのため、出力密度の向上につながる可能性があると考えています。
現在は界磁の調整範囲の拡大に取り組んでいます。
 図5:可変界磁同期機の図
図5:可変界磁同期機の図
【4】永久磁石を適用したハイブリッドスイッチトリラクタンスモータ(HBSRM)
スイッチトリラクタンスモータの固定子に永久磁石を配置し、高トルク密度化を目指したハイブリッドスイッチトリラクタンスモータ(HBSRM)の研究に取り組んでいます。トルク-電流特性等をシミュレーションと実験で評価・比較検討し、さらなる性能向上を目指しています。
本研究はテーマ(2)に関連します。また、株式会社ゲネシスラボ、富士電機株式会社との共同研究です。
 図6:解析モデル
図6:解析モデル
 HBSRMのモータベンチの写真
HBSRMのモータベンチの写真
 HBSRMの操作盤とアンプの写真
HBSRMの操作盤とアンプの写真
現在、蓄熱発電システムに用いる回転発熱機の研究に最も力を注いでいます。本研究は富士電機株式会社、一般財団法人エネルギー総合工学研究所との共同研究です。蓄熱発電システムは電気を熱に変換する電熱変換装置、熱を蓄える蓄熱装置と熱を電気に変換する発電装置から構成されます。代表的な電熱変換装置として抵抗ヒータが挙げられますが、近年、抵抗ヒータに対し、大容量化と低コスト化が可能と考えられる電熱変換装置として回転発熱機の適用が検討されています。回転発熱機とは、回転する発熱体ですので、どの回転機も回転発熱機に成り得ます。通常の回転機の出力は軸出力ですが、回転発熱機の出力は発熱量、つまり損失となります。そのため、回転発熱機は通常の回転機で言うところの損失が大きいほど高効率となります。
熱媒はエアギャップを通過し、回転子の熱を奪うことで昇温します。その際、軸方向のみならず、速度は1桁程度落ちますが径方向にも熱媒が流れます。そのため、乱流が発生することで攪拌による熱の伝達が著しく向上することから、抵抗ヒータに対し圧倒的な小型化が見込めます。
複数ある回転機の中で、誘導機が回転発熱機として適していると考えられ、誘導機を対象として解析を実施しています。本研究は、通常の回転機の高効率化と逆の発想で取り組んでいます。これまでにかご型誘導機と、円筒および溝付きのソリッドロータでの損失比較や、すべりに対する損失特性を解析により明らかにしました。
今後の課題として実機の製作と評価が挙げられ、2025年度に実施を予定しております。
 図7:蓄熱発電システムの図
図7:蓄熱発電システムの図
 図8:回転発熱機の図
図8:回転発熱機の図


図9:検討機の図
失敗しても良いから、まずは自分で考えてやってみよう!と学生には伝えています。特にシミュレーションでは物が壊れるわけではないので、考えたことをやってみて、出てきた結果をまた考えて、を繰り返してもらっています。また、表現は直接的でないにしろ、答えを教えて欲しいという学生もいますが、答えがわからないから研究していることを伝えています。
経歴の中で述べた「特に研究室に配属された後にどのような教育を受けると企業で活躍できるのか」について、研究活動の中で議論することが重要であると考えております。また、私自身は学生が言われたことだけをやる状態にならないように注意しています。
「想像力は知識よりも重要である。」想像力を働かせて研究に取り組んで欲しいと考えています。仕事とは、相手の事前期待を越えること。言われたことをやるだけでは進歩がないと思います。自分で考え、手を動かすことはとても重要だと考えています。
また、社会に出ると1人だけで仕事をすることはほとんどないと思います。そのため、コミュニケーションについて考え、それを実践することは、自身の成長につながるのではないでしょうか。
現在、複数テーマで三次元解析を実施しています。
WindowsデスクトップPCを最大限に活用し、三次元解析を効率よく並列実行したいと考え、並列オプションが豊富なPlan3に注目しました。
また、2つのテーマで同時に最適化に取り組む予定があったため、Plan3が最適だと判断しました。
将来的にライセンスを3つ追加する場合、並列数が8のPlan1を3つ購入するよりも、並列数が48のPlan3を1つ導入する方がコスト面でも有利だと考えています。
もちろん、ライセンス数を削減する必要が生じた際には、Plan1を買い直す必要があるため、そのような場合にはPlan1を3つにしておけば良かったと思うかもしれません。
アカデミックライセンス自体が非常にリーズナブルであることは承知していますが、Plan3によってさらにコストメリットが得られることを期待しています。
お話を伺った方

大口 英樹氏
大口研究室Webページ:
https://ohguchi-lab.ei.u-tokai.ac.jp/

『JMAGソフトウェア正規ユーザー(有償会員)』または『JMAG WEB MEMBER(無料会員)』でサインインが必要です。
『JMAG WEB MEMBER(無料会員)』へ登録することで、技術資料やそのほかの会員限定コンテンツを無料で閲覧できます。
登録されていない方は「新規会員登録」ボタンをクリックしてください。