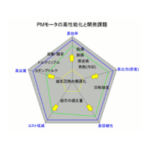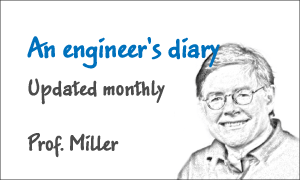モータ設計にFEAは有効か?
本稿ではモータを設計・利用されている方を対象に、シミュレーションを活用する効果を知って頂くことを目的としています。よりよいモータ設計のためにご参考頂ければ幸いです。
はじめに
本連載では、”なぜモータ設計に有限要素法電磁界解析(以下FEA)が有効なのか?”を解説してきました。第1回ではモータ設計の概念設計、初期設計段階におけるFEAの活用について述べ、初期設計からFEAを活用することにより、手計算では難しい自由度の多い設計案を高速に検討できることを示しました。第2回では詳細設計段階におけるFEAの活用として、細かい設計を詰めていくような試行錯誤でFEAが活用できることを紹介しました。最終回の今回はモータの中で起きている現象を詳しく把握するためのFEAの意義について紹介します。
実測は性能の良否を教えてくれるが、何が課題かは教えてくれない
概念設計を経て、詳細設計された開発品が設計通りの性能を発揮出来ているかを評価するために試作機を製作され、測定器やテストベンチなどを使用して性能が測定されます。例えば、モータはテストベンチで測定することで、狙った通りの出力特性が出たのかどうかにより、設計の善し悪しが評価されます。その結果は明白で、白黒がハッキリ出ますが、性能が出なかった場合に何が悪かったのか、どこを直せば良いのかまでは教えてくれません(図1)。測定結果を注意深く分析すれば、ヒントが見えてくることもありますが、設計要素(原因要素)は沢山ありますので、原因を特定するのは容易ではありません。
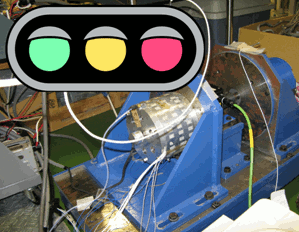 図1 実測は良否とヒントを与えてくれるが…
図1 実測は良否とヒントを与えてくれるが…
実測も簡単では無い
実測自体も簡単ではありません。例えば、モータは損失の低減、効率の向上が常に目指され、開発ニーズは更なる損失の低減を求めています。しかし、一昔前に比べればモータの効率は向上しており、最近は当たり前に存在している損失などの低減は大方片付けられており、よく目を懲らして見ないと見つけられないような損失を低減することに注目が集まっています。重箱の中のご馳走はあらかた食べ尽くされており、隅っこに何か残っていないかを探している状態です。
鉄損の測定を例にとって考えて見ます。理屈から考えると、鉄損はヒステリシス損と渦電流損に分離されますが、それぞれを直接測定することは出来ないため、測定結果を理論式に沿って分離しています。従来、積層コアの損失を測定するためにはエプスタイン法を用いた測定が利用され、JMAGの鉄損ツールもこのデータを活用することで鉄損を実用的な計算時間で得ることが出来ており、この手法は現時点でもある程度の精度を期待できるものを考えています。
しかし、モータの小型化、高性能化をより進めるため、従来は使わなかった高周波域、高磁束密度域で運転する場合が増えており、この運転域での鉄損にも注目が集まっています。この領域での損失には直流重畳が大きく影響しますが、エプスタイン法では直流重畳の影響が考慮されないため、高周波且つ高磁束密度時の損失の測定には不十分です。そのため、この結果を用いた解析の精度も不足することになり、精度を向上させるためには、何らかの手を打つ必要がありました。更に、高周波且つ高磁束密度時の損失を測定するためには高出力且つ高精度な電源装置が必要となるため、測定自体の難易度が上がっています(図2)。
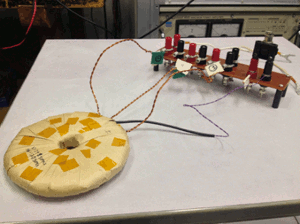 図2 リングコアの損失測定風景
図2 リングコアの損失測定風景
実現象の理解・分析を補強するためにFEAを活用する
そこで効果を発揮するのがFEAの活用です。FEAは理屈の上では、様々な物理現象をモデル化することで複雑な現象を解析することが可能です。現実的には”全ての物理現象をモデル化する”ことは極めて難しいことですが、寄与度の大きいと思われる物理現象や注目している現象に注目してモデル化する事でその影響度を予測することは可能です。
上記で例としてあげている、実測が難しい鉄損を知るために、FEAでは材料ヒステリシスループをトレースさせる、渦電流の挙動を直接解くなど、材料の振舞いを忠実にモデル化して解析を実施することは、それらの振る舞いを確認し理解する事を大いに助けるはずです。その解析結果と実験結果と突き合わせ、相互に補間することで、今まで理解出来なかった現象を理解可能となり、問題の対策を打つためのヒントを得ることが出来るはずであると考えています(図3)。
 図3 解析結果は要因分析を助ける
図3 解析結果は要因分析を助ける
予め、全ての物理現象についての評価を行い、設計されるような理想的な開発が行われれば、試作評価の段階で問題が発覚するようなことは無いはずですが、往々にして想定外のことが発生し、且つその原因が良くわからないというようなことが起きます。そのような状況でも実測結果と解析による予想を付き合わせ、使える情報は全て使い、原因特定を図って対策を打つことが、正しい取り組み方であると考えています。
実現象に近づけるために、理論に沿ってモデルの現実度を高めたJMAGの損失解析機能
“より詳細な現象を把握するためのFEA”を実現するため、ここでは、最近リリースしたJMAG-Designerの積層鋼板の材料損失の解析精度向上のための新機能について紹介します。
材料特性モデリング・鉄損の渦電流成分
FEAにより積層鋼板の渦電流を精密に解析するためには、鋼板1枚1枚をモデル化して解析することが理想です。しかし、実際には計算規模が莫大になるので現実的ではありません。この問題を現実的な計算時間で解く機能が”積層鋼板の渦電流損失計算機能”です。この解析機能自体はJMAG-Designer Ver.12.0でリリース済ですので、御存知の方も多いかと思いますが、改めて御紹介します。
本機能は積層鋼板の板厚方向の渦電流(表皮電流)を磁束密度の時間変化と材料の透磁率、電気伝導度、板厚から1次元的に求めており、2次元の解析結果からも渦電流損失を求めることが可能になります。2次元解析の場合、イメージ的には2次元+1次元になります(図4)。
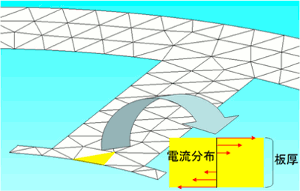 図4 積層鋼板の渦電流損失計算機能のモデル化イメージ
図4 積層鋼板の渦電流損失計算機能のモデル化イメージ
この手法は、板厚方向にはメッシュを生成しないので、計算時間を現実的な時間に抑えることが出来ます。また、3次元の解析モデルにも適用可能です。現実には存在する板厚方向に折り返す電流が無視されることや面内渦電流と区別して取り扱う必要があることなどの欠点はありますが、従来の鉄損解析ツールでは不可能な、過渡解析中での鉄損の渦電流分を見込んだ解析までを行うことが可能です。
実測(エプスタイン法)の問題として高周波、高磁束密度の測定が非常に難しいことが上げられます。この領域の測定を行う為には、前述の通り高周波において、高品質且つ大電流の電源が必要になります。しかし、実際にそのような電源は入手が難しいため、低周波数での測定結果から、周波数の2次関数として外挿により測定範囲外の高周波の損失を求めます。そのため、周波数が高くなるほど上振れする傾向が強く、誤差を生む要因となっていました。
積層鋼板の渦電流損失計算機能では、渦電流損失をほぼ直接解く形になりますので外挿する必要はなく、周波数の上昇に伴って表皮厚が薄くなる現象も織り込むことが可能になるので、精度の高い渦電流損失を求めることが可能となります。本機能と実測結果を突き合わせることで損失の高精度な損失の把握が可能になり、課題の解決の助けになると考えています。
材料特性モデリング・鉄損のヒステリシス成分
渦電流同様、ヒステリシス損失の解析精度向上のための機能をご紹介します。現象のモデル化のポリシーは、言うまでも無くヒステリシスきちんと追って解析することになります。
最近、PWM駆動される機器が増えていますが、PWM駆動の場合、機器に投入される電流波形は基本波に加えてスイッチングによる時間高調波が重畳される形になります。したがって、ミクロに見ると基本波により直流オフセットしているところに時間高調波で振動している形になります。そのため、磁気回路の動作状態も直流重畳されたマイナーヒステリシスループを巡ることになります。
エプスタイン法の測定は0点周りの交番磁界を加えて損失を測定するため、直流重畳した効果を評価することは出来ていません。比較的飽和していない動作状態であれば、直流重畳によりオフセットしたとしても影響は小さいですが、ケイ素鋼板の飽和域を使うようになると急激にヒステリシスループが大きくなってしまいます(図5)。そのため、直流重畳された場合と、されない場合でヒステリシス損失が異なってきます。
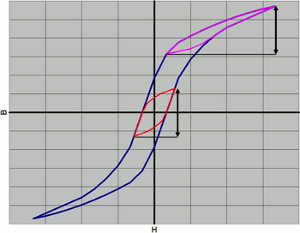 図5 ヒステリシス損失のイメージ
図5 ヒステリシス損失のイメージ
最近の電気機器は小型化を推し進めるために、動作磁束密度を高くして、ある程度の磁気飽和はやむを得ないと考えて設計される場合が多く、PWM駆動の影響と相まってヒステリシス損失が想定よりも大きくなってしまう危険性が増えています。
JMAG Designer Ver.12.1からヒステリシスのマイナーループを考慮して磁界解析を実行する機能を実装しました。以前まではユーザーサブルーチンを使っての実行となっていましたが、今回からユーザーインターフェース上から設定可能となっています。課題となる材料ヒステリシスループの生成に関して、ユーザー自身がループを点列で定義する方法の他に、鉄損特性を持つケイ素鋼板に限っては、その材料データを活用して自動でヒステリシスループを生成する機能を実現しました。
形状モデリング・磁石渦電流損失の評価
永久磁石モータでは磁石の渦電流損失による磁石の温度症状とそれに伴う特性低下も大きな問題になります。磁石は回転子に組み込まれることが多く、回転中の磁石単体の損失はもとより、温度測定が技術的に難しいといえます。
この損失を解析で見込むためには、理想的には三次元解析を行い、磁石に流れる渦電流を模擬した解析を行うべきですが、三次元解析は計算規模が大きくなるため、実用的ではありません。第2回でもご紹介しましたが、二次元解析の結果を利用して、回転子部分のみ三次元解析を行う磁束密度境界条件を利用することで、実用的な計算時間で精度の高い磁石の損失を算出することが出来ます(図6)。
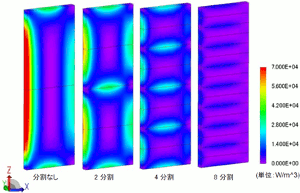 図6 磁石渦電流損失による発熱分布
図6 磁石渦電流損失による発熱分布
形状モデリング・漂遊負荷損算出のための機能
磁石渦損と同様な重箱の隅の損失として、漂遊負荷損があります。例えば、漏れ磁束やコイル端部がモータケースに生じさせる渦電流損が代表的です。これらの損失は比較的小さいこともあり、個別の測定が非常に難しくなります。
したがって、解析により損失を算出し、事前には定量的に小さいことを確認しておくことが重要となります。事後に損失が設計値を超えている事を確認した場合は、想定外の箇所に漂遊負荷損が生じていないかチェックすることになります。
漂遊負荷損はモータケースなどに生じるので、解析する場合はモータを構成する全ての部品をモデル化する必要があり、必然的に三次元解析を行う事になります。JMAGでは三次元解析での計算精度を確保しつつ計算規模を抑えて、漂遊負荷損を求める事をサポートする機能として以下の三つの機能を実装しています。
- 拡張スライドメッシュ
- 積上げメッシュ
- コイルエンド作成機能
拡張スライドメッシュ生成機能は、従来の円筒スライドメッシュが使用できなかったモータカバーがオーバーハングしているような形状でもスライドメッシュを使用できるようになります。このため、パッチメッシュを使用した場合よりも安定して渦電流を求める事が可能になります(図6)。
積み上げメッシュ生成機能はモータの様な金太郎飴状の形状を認識すると、その部分には二次元+押し出しで三次元メッシュを生成しますので、円周方向と軸方向の分割数を適切に設定する事が可能になります。この効果により、三次元モデルの計算精度を確保しつつ要素数の増加を抑える事が出来ます(図7)。
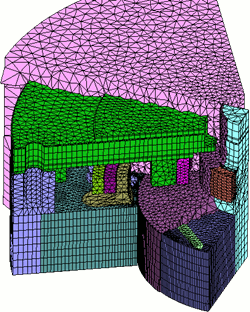 図7 拡張スライドメッシュと積み上げメッシュの組み合わせ例
図7 拡張スライドメッシュと積み上げメッシュの組み合わせ例
コイルエンド生成機能は、CADでも形状作成が難しいコイル端部のソリッドを簡単に作成する機能です。漂遊負荷損を考察のためには、コイル端部が作る磁界の影響を評価することになるので、コイルエンドのモデリング機能は必要になってきます(図8)。
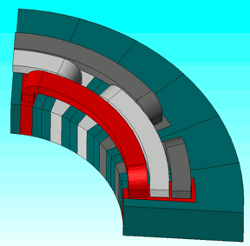 図8 コイルエンドテンプレートにより作成した形状
図8 コイルエンドテンプレートにより作成した形状
これらの解析機能により、漂遊負荷損の評価が容易になってきています。
詳細解析を実現するための計算速度向上策
これらの高精度計算は計算規模が大規模化することは避けられません。そのため、大規模モデルを高速化に処理するソルバーが必須となります。JMAGではソルバーの高速化を図るために、計算手法の見直しを行うと共に、ハードウェアの能力を引き出す事にも注力しています。複数CPU/コアに計算を並列処理させて高速化するSMPやDMPは今や一般化して皆さんも御存知と思いますが、画像処理用のGPU(Graphic Processing Units)を用いて高速に計算させることも出来る様になりました。
これらのモデリング技術の開発、計算技術の開発により解析精度が向上していますので、実測データの分析をより強力にサポートが出来る様になってきています。
損失以外の詳細解析機能
損失を精度良く算出する機能を中心にご紹介しましたが、JMAGでは損失以外についてもより詳細な解析を行うことが出来ます。例えば、構造解析と組み合わせることで応力による磁化特性の劣化を考慮する事や、熱流体解析を他のアプリケーションとの連成解析をより簡便に行えるように開発が進んでおり、複数の物理領域に跨がった検討を行いやすくなっています。
おわりに
三回に渡って、モータの開発においてFEAが有効であることを紹介させていただきました。JMAGは日々機能改善と性能向上を図っておりますが、JMAGを使用される方々からの要求も高まるばかりなため、いつもで経っても追いつかないのが現状です。我々は皆様の要求に引き離されないように開発を続け、少しでも皆さんのお役に立てるツールを提供していきたいと考えております。
[JMAG Newsletter 2013年6月号より]