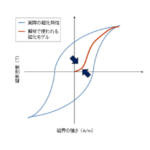解析屋が見た損失評価
山田 隆
晴海1号での検討によって負荷時であっても損失が予測可能であることを示すことができました。損失解析を行うユーザも増えてきて、合う合わないの大雑把な議論から、精度何%へ議論になってきました。昨日まで損失解析なんか信用できん、と言っていた人が今日は、5%未満の精度が必要だ、と言います。なんてフレキシブルな人。
精度を追求するためには、何が起こっているか理解しないといけません。晴海1号プロジェクトはどのくらい合わないか、問題を白日の下に引きずり出すことが目的だったのですが、”残念”なことに測定とよく一致してしまい引きずり出すことに”失敗”しました。それでは、なぜよく一致したのでしょうか?それについて考える必要があります。
分析のために損失をコアのヒステリシス損失、渦電流損失および磁石の渦電流損失に分離してみます(図23)。
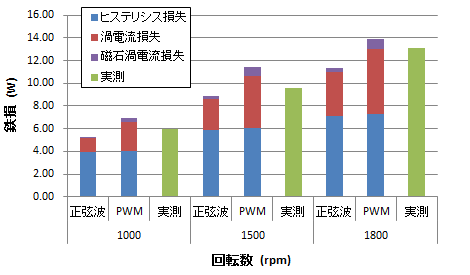 図23 ヒステリシス損失と渦電流損失の内訳
図23 ヒステリシス損失と渦電流損失の内訳1,000(r/min)から1,800(r/min)まで回転数ごとに、鉄損に占めるヒステリシス損失と渦電流損失の内訳を示す。
正弦波駆動とPWM駆動を比較する特に1,800(r/min)において両者の渦電流損失の差が大きくなっている。
前回も述べたとおり、損失全体で見るとPWMによる高調波の有無によって特に高回転域で差が大きくなっているのがわかります。その影響は損失分離の中を見ると、ヒステリシス損失ではなく、渦電流損失に現れています。今回のケースでは磁石の渦電流損失は比較的小さいのでしばらくの間、コアの鉄損に注目します。
ヒステリシス損失が高調波の影響を大きく受けていない理由は、周波数依存性が渦電流損失に比べて低いこと[*1]、および今回の場合、PWMによる高調波の振幅が基本波に比べて非常に小さいためであると考えられます(図24)。
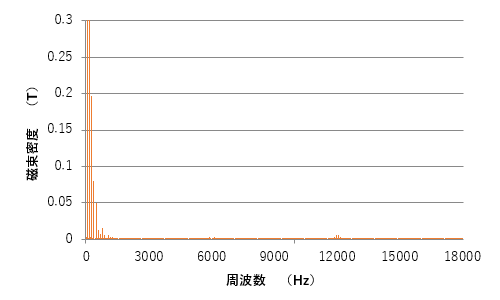 図24 ステータティース中央部の磁束密度の調波分析
図24 ステータティース中央部の磁束密度の調波分析電流振幅 4Arms、電流位相 10deg、回転数 1500rpm、キャリア周波数 6kHzにて計算。
わずかに高調波成分が見えるが、高調波成分の振幅は基本波に比べて小さくヒステリシス損への影響は大きくないといえる。
ヒステリシス損失の大部分を担うステータではゼロを中心とした交番磁束が主成分になっており、ヒステリシス損失は波形には依存しないことを思い出せば[*2]、従来の解析手法でも誤差の小さい結果を与えることがわかります。ただ、ロータ側は磁石によるバイアスがありますので損失はマイナーループによって発生しており(図25)、測定による確認はできませんが大きな誤差を含んでいるはずです。
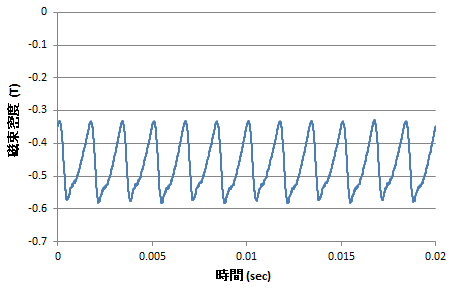 図25 ロータ表面の磁束密度波形
図25 ロータ表面の磁束密度波形晴海1号IPMモータのロータ表面での磁束密度径方向成分の波形を表示。磁石の起磁力により磁束密度波形はバイアスして変動。
そのため磁化特性の動作点はマイナーループを描くことになる。
一方、渦電流損失は周波数依存性が強く波形依存性も強いことからPWMの影響を受けやすいのですが、逆に言うと正しい電流波形を入力し、発生する周波数での損失値をデータとして持っていれば正しい結果を得られることができます。今回の場合、PWMのキャリア周波数は6KHzで、鉄損特性は1kHzまでしか持っていないため、範囲外の高い周波数については補外しています。今回は、その補外がうまく機能したことになります。それにしても、図25を見るとPWMによる高調波の磁束密度振幅は非常に小さいことがわかります。それが損失に大きく影響していることを考えると、周波数依存性を大事に扱わなくてはいけないことがわかると思います。
この考察、少々話を単純にし過ぎているかもしれませんが、本質は捉えていると思います。これによって、晴海1号のケースで測定値と比較的良い一致が得られたことを一般的に説明できたと思います。しかし、次の2点については課題を抱えていることも見えてきました。
(課題1)マイナーループによるヒステリシス損失
(課題2)測定データがない周波数領域における渦電流損失
今回のケースでは目立ちませんでしたが、課題1はSRモータのように半波で駆動するような場合には深刻な問題を引き起こしますし、課題2も高回転域では避けられない問題を生じます。
これまで話がうまく行きすぎて従来の解析手法に頼りきりになっていましたが、上の課題は、従来手法の原理的な限界を示しているようです。今度こそ新しい技術プラットフォームを乗り換えないといけないようです。
従来の解析手法の根本的な問題は、モデルの動作域が材料測定の時点で決められてしまい、その動作域以外での精度は保障されないことです。この問題を解決するためには、測定された鉄損特性をそのままモデルにするのではなく、損失発生メカニズムを再現するようなモデルをつくり、材料特性は別途内部パラメータとして与える必要があります(図26)。
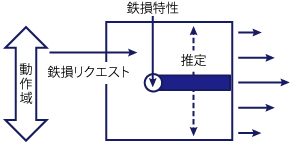 (a) 従来の鉄損モデル
(a) 従来の鉄損モデル特定の動作域で測定した損失値を、解析時の動作域に関わらず、そのまま使用するため、リクエストされた動作域がずれると信頼性が低下する。
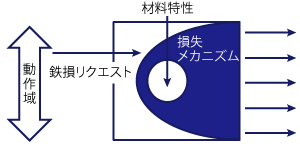 (b) 新しい鉄損モデル
(b) 新しい鉄損モデル損失メカニズムを内蔵し、あらゆる動作域に対し信頼性を維持する。材料特性は損失メカニズムを特徴づけるパラメータとして使われる。
中央の四角が鉄損モデル。左から入力される鉄損リクエストに対し、鉄損を右に出力する。鉄損出力矢印の長さは信頼性を表している。
ではその新しい鉄損モデルはなんだろう、と世の中を見渡してみるといろいろと素晴らしいモデルが提案されています。しかし、実用的な見地から見た場合、次の要求を満たしてもらわないと困ります。
(要求1)鉄損モデルに使われるパラメータの測定からの同定が容易
(要求2)計算時間が現実的
検討を重ねた結果、ヒステリシス損失に関してはプレイヒステロンモデル、渦電流損失には均質化法を採用することになりました。それらについては次回お話ししたいと思います。
[*1] 第3話8式
[*2] 第3話図5